【仙台 司法書士】稲辺司法書士事務所|不動産購入のアドバイス
【仙台 司法書士】稲辺司法書士事務所|インフォメーション
消滅時効の援用について
2017.10.16
破産者の連帯保証人になっていた方から、御相談を頂きました。
最終の支払日から、既に7年以上経過しており、本来であれば商事消滅時効の援用が可能な事例でした。
しかし、主債務者の方が、3年前に破産しているとのことでした。
保証債務は、主たる債務に附従しますので、主たる債務が時効消滅すれば援用することができます。
破産手続において、破産管財人に対して債権届出がなされ、債権表に記載されますと、確定判決を得たのと同様の効果が生じます。
判決による債権は、時効期間が10年となり、3年前の破産手続であれば、消滅時効は完成していない事となります。
又、手続が終了し、主債務者が免責を得ていれば、履行請求ができない債権のため、時効の起算点がなく、主債務の時効進行を観念する余地が無く、保証人は主債務の消滅時効を援用できないと、されています。

相続放棄? 限定承認
2017.09.13
昨日、某信用金庫の支店長からこんな相談を、受けました。
ご主人が亡くなり、奥様と子供さんが相続放棄をしたそうです。その方の自宅は、土地が亡くなったご主人名義、建物が奥様名義です。
亡くなったご主人は、無担保の債務が400万円ほどあり、その他信用金庫の債務もあったので、弁護士が相続放棄の手続を、行ったそうです。
その弁護士は奥さまへ、今後支払う必要は無いと告げたそうです。
ところが、信用金庫の債務は、奥様も連帯債務者であり、当然支払う必要がありました。
信金の支店長が、そのことを弁護士へ告げたところ、弁護士は動揺し、意味不明の言葉を、並べていたそうです。
ここで問題なるのが、自宅の底地です、御兄弟も全て相続放棄しており、このままであれば、債権者が強制的に競売してしまいます。(担保的に余力があるようでした。)
そこで、どうすれば底地を取得できるかとの相談でした。
方法としては、亡くなったご主人様の相続財産管理人を、選任請求致します。
奥様は建物の所有者ですので土地の使用料等支払い義務があります。利害関係人として、選任請求ができます。
そのうえで、相続財産管理人との間で、底地の売買契約を締結するのです。
その場合の金額を試算すると、600万円程度でした。
400万円の債務を逃れるため、600万円を、支払う結果となるわけです。
このような事態を防ぐには、限定承認の方法をとれば良かったのです。
もっとも、信用金庫の債務内容を、確認しないのは問題ですが・・・・・

農地の所有権移転
2017.08.11
農地の売買について、ご質問を頂きましたので、簡単にまとめてみます。
登記について言えば地目が農地(畑、田)の場合にのみ問題となります。農地法は現況主義ですが、登記官には形式的調査権しかありませんので、現状畑であっても、地目が宅地、雑種地等であれば、通常の移転登記と同じ手続きで済むからです。(農地を無許可で、現状変更することは違法ですので注意してください。)
地目が農地の場合、農業委員会へ届出を、行い許可を得る必要があります。
農業委員会の許可証は、移転登記の添付書面であり、所有権移転の効力要件です。
ご質問いただいた銀行の方は、以前はすぐに手続きができたのに、今回は何故時間がかかるのか?とのことでした。
これは市街化区域内とそれ以外の場所という、不動産所在地の違いによるものです。
市街化区域においては許可までは必要がなく、届出のみで足ります。そして登記の添付書面は、届け出の受理通知のみでOKです。
ご質問をいただいた銀行の方は、前回市街化区域内の移転であったため届出のみだったのでそれほど時間を要しなかったのでしょう。
市街化区域以外ですと、通常締切日が決められており(仙台市だと毎月20日)ひと月分をまとめて翌月に、農業委員会で審議し、許可の可否を決定します。そのため2〜3ヶ月の時間を、必要とします。
又、許可(原則は不可な事を、特別に認める)ですので、場所、計画によっては、不許可の決定となることもあります。
宮城県内で、市街化区域を設定しているのは、仙台市、多賀城市、富谷市、名取市等です。大崎市や大河原町、亘理町等は、非線引きのため注意を要します。

相続放棄について注意するべきこと
2017.07.24
昨日、昔からの知人が亡くなり、お通夜に行ってきました。
その時、故人の奥様から、葬儀費用、故人の医療費支払いのため故人の預金口座から払出しの可否を、尋ねられました。
故人には借財が有り、亡くなった時は、相続放棄するよう話されていたという事でした。
故人の預金を払い戻して使用することは、単純承認したことになります。
但し、葬儀費用は相当な程度(社会的に身分相応な程度)であれば、単純承認にあたらないとされています。
万難を排する為、払出しはしないようアドバイスをして、しつれいいたしました。

破産事件の難しさ
2017.07.20
先日、書面作成した破産事件が免責決定がおり、終了致しました。
現在、給与所得者という事で、同時廃止で申し立てした事件でしたが、過去の支出に不透明な事項が多いとして、管財事件となっていたものです。
書面作成者として、できるだけ十分に聴き取りをしたつもりでした。
しかし、管財人の先生が調べてみると、色々な事項が判明し、自分の聴き取り不足を、痛感致しました。
書面作成の場合、どうしても軽くみられてしまうのかもしれませんが、債権者へ迷惑のかかることのないよう、十分なヒアリングが必要だと、改めて反省致しました。

個人民事再生 一関
2017.05.26
個人民事再生申立書(小規模個人再生)を、盛岡地方裁判所一関支部へ提出しました。番号は再イの第3号として、手続進行表が送られてきました。
かって、古川支部、気仙沼支部へ提出したときは、いずれも秋(10月から12月頃)でしたが、第1号でした。
個人再生が普及してきたのでしょうか?
債務の整理方法としては、破産より、本人の精神的な負担も少ないので(経済的な負担はありますが)、当事務所としてはできるだけ個人民事再生を、お勧めしております。
良い傾向だと思うのは、考えすぎでしょうか?
ちなみに、再生委員は選任されておりません。
本人の負担も軽く、良いことだと思います。

法定相続情報証明制度
2017.05.18
5月29日から、法定相続情報証明制度が始まります。
これは、戸籍等を添付しなくとも法務局発行の法定相続情報一覧図(認証文付き)を添付することにより、相続手続(預金、株式、不動産等)が可能となるものです。(分割協議書等は必要)簡単にいえば戸籍一式の代わりになるものです。
当事務所で相続登記を、ご依頼された場合には、無償で作成致しますので、お申し付け下さい。

募集有り難うございました
2017.05.18
事務員さんを募集致しておりましたが、ハローワーク経由で、この度新しい事務員さんに、入所いただきました。
ご応募いただいた皆様、有り難うございました。
新しい事務員さんは、法律事務所に長い間勤務された方ですので、皆様にはより良いサービスを、提供できるものと考えております。

事務員さん募集
2017.04.08
当事務所では、現在事務のお手伝いをしていただける方を、募集致しております。
勤務形態は、フルタイム、あるいはパートタイムのいずれでも結構です。
必要なスキルは、PCの基本的操作、ワード、エクセルの操作です。司法書士事務の経験は、なくとも結構です。
勤務時間は、フルタイムの場合、9時から18時まで(1時間の休憩有り)、パートタイムの場合は、9時からで、終了時間は御相談に応じます。
フルタイムの場合、残業は一切ありません。(私がサラリーマンの頃、残業は嫌でしたので、今の事務員さんにもお願いしたことはありません。)又完全週休2日制です。
パートタイムの場合、時給は800円からになります。
詳細は、お問い合わせ下さい。

法テラス利用のお勧め
2016.12.09
現在、当事務所では毎月1〜2件程の、破産申立を、行っています。
依頼者の方は、多くが法テラスを利用されています。
法テラスは、法律上の手続を行う費用が無い方に、国が一時的に費用を立替える制度です。
単身者であれば、年収220万〜230万位迄、利用が可能です。借入金で苦しんでいらっしゃる方は、一度当事務所まで御相談頂ければ、お手伝いができるかと思います。

重要事項説明
2016.11.17
最近多いのが、不動産の売買契約締結後に、登記費用の見積もりを、依頼されたり、契約内容について質問を、受けるケースです。
宅地建物取引業法では、契約締結前に重要事項説明をするように規定しておりますが、実務では同時にしている事が多いようですので、そのためかもしれません。
不動産購入時の一番のポイントですので、仲介者へ依頼し、早めに説明を受けることを、お勧めいたします。

株主リストについて
2016.09.23
28年10月1日から、商業登記規則が一部改正施行されます。
登記すべき事項について、株主全員の同意、株主総会の決議を要する場合、「株主リスト」の添付が、必要になります。
「株主リスト」とは、株主全員の同意を要する場合は、全株主につき、株主の住所、氏名、株数、議決権の数を、記載したものです。
株主総会の決議を要する場合には、同じ内容を記載したリストですが、全員分は必要なく、議決権の割合が高い上位10名あるいは、議決権の割合が3分の2に達するまでの人数の、少ない方でOKです。
商業登記は性善説で運用されていたのですが、色々不正等があったのかもしれません。
急に準備するのは大変ですから、株主名簿はキチンと整理しておいた方が良いようです。

同時廃止と管財事件
2016.08.26
破産についての、御相談が多くなってきています。
その時によく質問されるのが、同時廃止となるか、管財事件となるかについてです。
破産申立をした場合、管財事件とするか同時廃止事件で、処理して頂けるかは、裁判所の判断です。
原則は管財事件ですので、破産申立時にはできれば予納金の準備を、お願いしたいのです。
裁判所では、法テラス利用の方に対しても、管財とするケースが多く、苦慮しております。
できるだけ、早めの御相談を、お願い致します。

事前通知と本人確認情報
2016.07.30
7月のはじめに仙台法務局と司法書士会仙台三支部の打ち合わせがありました。
法務局からの連絡事項の中で、注意が必要だと感じたのは、本人確認情報制度です。登記識別情報・登記済証を添付しないで権利の変更登記を申請した場合登記義務者へ通知し、義務者から登記が真正である旨の申し出を受けなければ、登記ができません。(事前通知制度 不動産登記法第23条第1項)
この場合、決済を同時に且つ安全に行うために利用されるのが、本人確認情報制度です。
これは申請を行う、資格者代理人(司法書士・弁護士等)が本人に間違いない旨の書面を添付して、事前通知ではなく処理してもらう制度です。
今回法務局が、注意したのは本人確認情報の提供があっても、登記官の判断により事前通知とすることはあり得るという事でした。
改めて条文を読んでみますと、不動産登記法第23条第4項は、次の各号の場合は適用しない(同条第1項を)としており、1号で、本人確認情報について述べ、最後の文章として「かつ、その内容を相当と認めるとき。」と結んでおります。
今後は、本人確認情報の作成に一段と注意し、説明を慎重にしなければならないと、改めて肝に銘じました。

代襲相続について
2016.07.23
相続は、配偶者と血族相続人にその権利があります。血族相続人が被相続人(亡くなった人)より先に亡くなっている場合、血族相続人の子(孫、甥、姪)が、相続する代襲相続という規定があります。(民法887条2項、889条2項)
先日、兄姉の孫は相続人になるのか?との質問を、頂きました。
この場合、代襲相続であれば兄弟姉妹の子までしか認められていないため(889条2項は、887条3項を準用していない為)相続人とはなりません。
しかし、代襲相続では無く、通常の(?)順番で相続が発生していた場合、兄弟姉妹の相続分を、相続していれば相続人となります。
又、現行民法改正前(昭和55年12月31日以前)は、再代襲が認められていましたので、相続人となります。
具体的な事案毎の判断が必要ですので、戸籍をお持ちの上、司法書士に御相談くださるように、お願いしました。

デット・エクイティ・スワップ
2016.04.19
先月、デッド・エクイティ・スワップの、お手伝いをしました。
何の事?と事務員さんから質問されましたが、日本語で言えば、債務と資本の交換です。(私の英語はかなり怪しいので間違っていたら許してください)
司法書士の業務としては、債権現物出資による資本と株式数の変更登記です。
借りていた金銭を現物出資していただき、株式を発行して資本とするものです。
債務の株式化などと呼ばれることもあります。
債務を返済する代わりに、株式を渡して経営に参加していただくというイメージです。
登記手続的に、時間が無かったため、総額引受方式で行いました。
債権者が同意してくれれば、業務内容に魅力のある会社にとっては良い再建方法です。
近いうちにHP上で、手続等説明してみたいと思います。

上申書について
2016.03.22
先日、司法書士会から民事局通達が送付されてきました。(厳密に言えば会員用のWEBに掲載されました。)
相続登記をする場合、除籍等が滅失、あるいは保存期間満了(現在は150年ですが、平成22年までは80年でしたので)で、謄本を添付できない場合があります。このような場合「謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書と、相続人全員の上申書(「他に相続人はいません」という内容で、印鑑証明書添付)をつけて申請していました。
今回の通達は、市町村長の証明だけで良いというものでした。
相続人間の関係が希薄になり、相続人全員の上申書を提出することが困難になったからなのでしょうか?
ちょうど上申書を添付して申請しようとしていたので、複雑な気持ちになりました。
もう1か月早く通達していただければ、皆さんに余計な手間をおかけすることもなかったのですが……。

年末年始の営業について
2015.12.26
今年も1年間有り難うございました。
当事務所は、12月29日から1月3日までお休みを頂戴いたします。
営業開始は1月4日からとなります。
来年も宜しくお願いいたします。

債務整理の目安について
2015.11.09
景気が少し落ち込んでいるのでしょうか、債務整理、破産等の御相談が増えています。
私たちが債務整理で介入する場合に、方針をたてる基準となるのが債務の総額です。
任意整理の場合、通常債権者は60回までの分割返済を許容致します。債務総額が300万円であれば、月額5万円の返済になります。
通常はこの程度が支払いの限界です。つまり任意整理の上限と考えられます。
収入が、500万円を超えているようであれば、もう少しは払えます。
しかしそのような場合は、個人民事再生を、勧めています。
個人民事再生は、要件が厳しいのですが、債務総額を100万円まで圧縮できる可能性があります。(清算価値、債務総額等により異なりますが)
100万円まで圧縮できれば、月額3万円弱の支払いですみます。(返済期間は原則3年)
任意整理で債権者が60回(つまり5年)を、上限とするのは、人間が我慢して生活できるのが5年程度だからでしょう。

破産管財人の権利放棄不動産
2015.10.20
破産管財人が権利放棄した不動産の移転登記の、依頼がありました。
破産管財人が権利放棄しますと、個人の場合は、破産者の自由財産となりますので、破産者が売却できます。
法人の場合は、法人が処分できることとなりますが、破産決定時の代表者は、委任の終了により、退任することとなり新しい代表者を、選任する必要があります。
裁判所へ清算人の選任を、請求する事となり、その清算人が代表し手続きを行うこととなります。
この場合管財人が、権利放棄したことを証する書面が、添付書面となります。

財産分与
2015.10.05
最近、離婚に伴う財産分与の御相談が、増えています。
不動産を、夫婦共有で取得していた事から、離婚時に清算しなければならない事例や、連帯債務にしていたため、その債務を処理するための分与等です。
財産分与は、婚姻中の財産清算ですので、贈与税等についてはあまり問題となりません。しかし登記する場合には、評価額に対して2%の登録免許税が、必要となります。又不動産取得税も別に負担する必要があります。
財産分与については、離婚契約書等を作成し、今後紛争が生じないようにしておかれる事を、お勧めいたします。

保存行為としての登記
2015.09.10
後見人に就任する事が多いのですが、後見の申立事由は様々です。
時々残念に思うのは、相続登記のためという事例があることです。
もちろん、分割協議をする場合には、意思決定の能力が無い場合後見人を選任する必要があります。
しかし、単に相続登記をおこなうだけであれば、相続人の一人から申請することが、可能です。
もっとも、その後すぐに処分するのであれば、後見人の選任は必要ですが・・・
保存行為による相続登記の場合問題となるのは、申請人以外に識別情報が発行されないこと、次の相続(意思決定不能な人物が亡くなった場合です。)により権利関係が錯綜する事です。
上記の点についてクリアーできるのであれば、保存行為として登記することも検討するべきでしょう。

遺贈の登記
2015.08.21
最近遺贈による登記のご依頼が増えています。相続人が遺言により取得する場合でも、遺言書の文言が遺贈するとなっていれば、登記原因は遺贈となり、単独での登記申請はできません。(例外的に「相続人全員への財産全部を包括遺贈する」の場合は、原因相続)
遺贈の場合は登記義務者が、遺言執行者か、相続人全員となり、時間がかかります。
遺言書の作成時には、司法書士にも相談することを、お勧めいたします。

夏期休暇
2015.08.11
8月12日〜8月14日まで、夏期休暇とさせていただきます。
お急ぎのご用件は、司法書士の携帯(090−2844−7764)まで、ご連絡を、お願いいたします。

30年前の破産登記
2014.10.06
お客様が自分で申請した登記が却下されたとして、相談におみえになりました。
内容として、住所変更登記が未了である、登記済証が無い等がありましたが、35年位前の破産登記も残っていました。
裁判所に問い合わせたところ、記録が何も残っていないとのことでした。
管財人の先生が判明していたので、先生のご協力をいただき、裁判所へ上申し、抹消を嘱託していただきました。
裁判所の記録のない案件というのは、案外多そうです。

昔の仮差押登記抹消
2014.03.29
昭和60年ころになされた、仮差押登記の抹消依頼を頂きました。
仮差押は、裁判所の嘱託登記ですので、抹消するためには裁判所による判決(平成2年以前の仮差押に対する場合)決定手続きが必要となります。
仮差押は、あくまでも保全手続きですので、はじめに本訴をおこせという申立(起訴命令といいます)を、行い、その後保全取り消しの申立を、行う事になります。それ以外に事情変更による取り消しという手続きもありますが、裁判所と相談したところ、昭和60年は法律的にはそれ程昔ではないので、起訴命令手続きをとるべきではとのことでした。
世間に比べて法律の世界は、時間がたつのが遅いようです。

金融機関の事業目的の見方
2013.09.21
先日、地元金融機関の役員の方から登記の相談を受けた時のことです、融資審査に当たり事業目的が多すぎると何をしている会社かわからず、その時点で間に進める気力がなくなるというのです。
このことは、私も融資審査をしていたのでよくわかります。融資審査もリズムのようなものがあり、「借入目的、会社の概要、代表者の略歴、取引金融機関」などの基本的な事項は、すっきりと理解できないとその時点で、やや警戒的な気持ちになるのです。
登記上の事業目的を、やたら多く希望する方がいらっしゃいますが、借入を予定しているのであれば、本当に取り組む事業とプラス2つ程度にしておいたほうが無難なようです。
尚、目的変更は登録免許税3万円、司法書士報酬は2万円前後で可能です。

社宅と借地借家法
2013.08.26
社宅を利用している方が、解雇されたり、退職した場合借地借家法の適用があるのでしょうかとの、質問を頂きました。
社宅についてはその使用料金により考え方が別れます。
使用料金が、低額(1000円〜15000円程度?)の場合は適用が無いと考えられています。これに対して世間並みの賃料を支払っている場合は、適用があると考えられます。
但し、自分から退職を申し出た場合は、当然対象とはなりません。(自分から会社との関係を清算することを選択しているからです)

融資を受けるコツ 2
2013.07.08
ここ3か月の間に、融資のご紹介を、3件ほどさせていただきました。
いずれもローンが、他の銀行で否決された方達でした。
お話をよく聞くと、融資を受けられそうなのですが、不動産業者さんを間に入れてのお話で、断られていたようです。
直接銀行の方とお話しするか、若しくは一緒に出向いて話してみれば、もっと早くに融資を受けられたようです。
住宅ローンは、様々な規制があり、親族間売買等対象外のものも多いのですが、申込む方の属性がよく、返済比率等で問題なければ、プロパーで対応していただけることも多いようです。

渉外登記
2013.06.17
先日、スペインに居住している日本人のお客様から、所有権移転登記のご依頼が、ありました。
外国に居住している方の場合、住所を外国にもって行ってしまうと、当然日本の住民票は出ません。
このような場合、日本の領事館等で、住所地を証明する在留証明書を、発行してもらい住所証明書といたします。
海外居住者の方が義務者となる場合にも、日本の印鑑証明書は発行されません。この場合は署名証明書というものを、やはり領事館等で発行してもらい印鑑証明書に代えます。
署名証明書は、遺産の分割協議などでも使用いたしますが、署名する書類と合綴してあるものと、1枚署名だけを証明しているものとがあります。
以前、ケニア在住の方から、分割協議書と署名証明書を、送って頂いたことがありました。署名証明はローマ字で、分割協議書は日本語で記載されており、同一性が判明せず、取り直しを、お願いしたことがありました。
証明する書類と、合綴してあるものの方が、安心なようです。

登記名義人表示変更登記
2013.06.10
登記手続きので、頻繁に発生するのが登記名義人の表示変更登記です。
不動産を取得したときと、権利変動が発生したときに住所が異なる場合に、これを一致させる登記です。
不動産登記では、T市S二丁目に住んでいる山田花子さんと、T市S三丁目に住んでいる山田花子さんは別人ですので、同一であるという証明(通常は前の住所が記載された住民票)を、添付して住所の変更を、おこないます。
先日、離婚による財産分与の移転登記のご依頼を、頂戴いたしました。
ところが、調停期間中に住所を、移転しているのです。
そのため、調停調書に記載された人物とは別人になってしまっています。
このような場合に、義務者(権利を失う人)の場合は表示変更登記が必要になります。

相続放棄について
2013.05.27
先日、お母様が亡くなってから6か月ほど経過したかたの相続放棄申述書と、上申書を作成いたしました。
相続は、自己が相続人であることを認識したときから、3か月以内に放棄、あるいは限定承認の手続きを取らない場合には、承認したものと見なされます。
但し、被相続人に財産、債務がないと信じていた場合には、3か月経過後の放棄手続きが認められることもあります。
今回の依頼者の方は、お母様が保証人になっていた事を知らず、6か月経過した時点で保証債務の相続人であることを認識したケースでした。
事情を詳細に記載した上申書を添付した結果、無事申述書は受理されました。

農地の売買
2013.03.29
地目が畑となっている土地について売買のご相談を、いただきました。
地目が田、畑などの場合相続、判決による移転などを除き、原則として農地法の許可が必要となります。
ご相談いただいた方は、前に売買したときには必要がなかったと主張されました。
よくお話を聞くと、前におこなったという売買は、仙台市内の市街化区域内のようでした。市街化区域内の場合は、農業委員会への届出だけで、(届出の受理証の添付のみ)移転登記は可能です。
しかし今回は大和町の調整区域でしたので、許可が必要だということを説明させていただきました。

融資を受けるコツ
2013.02.04
よくご相談をいただくのが、どうすれば融資を受けられるか?という質問です。
新しく会社を設立した場合、すぐに融資を受ける為には、個人事業主としてあるいはサラリーマンとして同一の業種についていたことが必要になります。
金融機関も経験のない業務には、中々融資はしません。
もう一つ大切なのは経営計画です。但しこれはすぐにできるものではありません。又、第三者につくってもらったものでは、ヒアリングを受けたときに馬脚を現します。
専門家と相談しながら、自分なりに実現可能なものを作成しておくことを、お勧めいたします。
最後に重要なのが、あまり直前に申し込まないということです。
金融機関は急ぐ融資をいやがる傾向にあるからです。

内容証明郵便について
2013.01.29
建物明渡し、債権回収などの依頼におみえになるお客様の中に、ご自身で内容証明郵便を発送してからおいでになる方が、多くいらっしゃいます。
配達証明までおつけになっており、よく勉強されている方が多いのですが、文面の中に必ず入れておいていただきたい文章が抜けていることが多いのも事実です。
建物明渡しであれば、催告と解除、債権回収であれば、期限と債権発生理由等です。
内容証明郵便から行ったとしても、費用的には2万程度の負担増です。
再度発送する手間などを、お考えいただければ早めにおいでいただき、お任せいただいた方が、解決には早道かと思います。

1年間ありがとうございました。
2012.12.28
当事務所は、12月29日〜1月3日の間お休みをさせていただきます。尚、メールでの相談は、その間もお受けいたしております。
1年間有り難うございました。来年はホームページを、リニューアルする予定ですので、引き続き宜しくお願いいたします。

敷金の返還について
2012.12.01
先日、敷金が返還されないとの相談がありました。返還どころか追加で原状回復費用として10万円あまり請求されたという事でした。
原状回復費用は住宅の賃貸借の場合、基本的には貸主の負担となります。
それは、賃料の中に、通常使用すれば損耗する劣化費用や、年数が経過することによる劣化費用も含まれているとの考え方によります。
多くの場合ハウスクリーニングについては、借主の負担とするという特約が契約書上記載されています。
しかしこの特約については、ハウスクリーニングを、行う必要性があり、その費用、範囲が明示されていなければなりません。
今回のお客様も、最終的には子どもさんが落書きをした襖の張り替え等、4万円のみの負担ということになり、敷金のうち8万円は返還されました。

お問い合わせについてのお願い
2012.11.16
最近メールでのお問い合わせを、よくいただきます。
その場合返信してもエラーとなるケースが多く見られます。又、お問い合わせ自体が、迷惑メールに振り分けられていることも多くあります。
無料のメールサービス等を、ご利用になられている場合が多い様です。
確実にご連絡させていただくためにも、連絡先については、電話番号と、ご都合の良い時間を併記していただければと思います。

財団法人について
2012.10.29
先日、企業からの寄付を仲立ちする業務を行いたいが、財団法人を設立するべきかとの質問をいただきました。
その方は、商品の販売時に、寄付金をプラスして受領し、そのお金を東日本大震災の被災者に交付するという事業を考えていらっしゃいました。
非常に良いアイデイアで、社会貢献にもなります。(内閣府の社会起業インキュベーション事業にも認定されているとのお話でした。)
問題は財団法人で可能かとの部分です。
財団法人は、お金の集団です。はじめに一定額のお金が必要になります(法律では財産に法人格を与えたものとしていますが、わかりやすくお金としました。)
設立後も一定の金額が確保されている事が条件となります。
お問い合わせいただいた方は、多額の財産は用意することが困難との事でしたので、社団法人をお勧め致しました。

遺産分割の事前調査
2012.10.01
遺産分割の前提として、被相続人がどの程度預金を保有していたのか知りたいとのご相談をいただきました。
相談者の方は、仙台に居住しており、お亡くなりになったお母様は、弟さんと東京で、同居していたということでした。
弟さんが何も教えてくれず、お母様の資産内容がわかないが、不動産の処分もあり、遺産分割調停を申し立てたいとのご依頼でした。
預金残高を知る方法としては、取引銀行が判明していれば、被相続人死亡の記載がある戸籍と、相続人であることを証明する戸籍を銀行へ持参し、被相続人死亡の事実を告知し、預金の残高証明を依頼すれば発行してくれます。
死亡の事実を告げることにより、同居している相続人による預金の使い込みが防止でき、今後調停等が進めやすくなります。
銀行によっては、取り扱い支店でなくとも可能な場合がありますので、問い合わせてみるべきでしょう。

ユニワードについて
2012.09.17
先日、ユニワード(本店が盛岡にある貸金業者)に対する過払い金返還請求の第1回口頭弁論がありました。
ユニワードは、判決を取得しても支払をしてこないと聞いていたのですが、お客様の要望もあり提訴いたしました。
答弁書の提出もなく、被告が欠席したため1回で終了いたしました。その場で裁判官、書記官が話していたのですが、ユニワードは被告の場合(過払い金請求の場合だと思いますが)は答弁書も提出せず、欠席することがほとんどだとのことです。
反対に原告(貸金請求事件だと思います)の場合は、結構執拗に請求してくるとのことでした。
過日、金融業に勤務していた身としては、いささか納得できず、情けない感じがしました。

遺産分割協議書
2012.09.01
現在相続人が17名という相続登記を、行っています。
相続人は北は青森から、南は大分県までいらっしゃいます。このような場合分割協議書を、一枚で作成するのはあまりに非現実的です。
このような場合、同じ内容の協議書を作成し、それぞれの相続人へ郵送し、返送していただくようにしています。(実質的な内容が同一であれば、表現は若干異なっていてもOKです。)
この点先日後見人として手続きをした、ゆうちょ銀行の手続きは必ず同一書面でなければならないということで、大変苦労いたしました。
実務的な視点で再考していただきたいものです。

夏期休暇について
2012.08.11
当事務所は、8月13日〜8月15日の間、夏期休暇を取らさせていただきます。
お急ぎの場合は、司法書士の携帯電話090−2844−7764迄ご連絡を、いただければ対応いたします。宜しくお願いいたします。

遺言書のある場合の登記
2012.07.22
遺言書がある場合、相続・あるいは遺贈による移転登記は、承継者が相続人であることの書面のみで十分で、被相続人の出生から死亡までの戸籍により相続人全員を、特定する必要はありません。
但し遺言書の添付が必要であり、公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所の検認を受け、検認証明書を添付する必要があります。

電子定款の認証
2012.06.22
先日、ご自分で会社設立をなさろうとしている方から、定款の認証についてご質問を、頂戴いたしました。
その方は、CDに定款を入れて公証人のところへ持って行けば、認証ができるとお考えの様でした。
電子定款を公証人に認証していただくためには、定款をPDFにし、作成者が電子署名しなければなりません。
電子署名した定款を、法務省のシステムに送り、公証人はその内容を確認したうえで、持参したCDに認証済の電子定款を入れてくれます。
電子署名自体あまり使用する機会もないと思いますので、定款認証については専門家に依頼する方が時間の節約になると思います。

遺産分割協議書
2012.05.16
昨日、銀行の方から相続登記に遺産分割協議書は必ず必要なのかとの質問をいただきました。
相続登記をする場合、①法定相続分に従って登記する場合、②遺言により相続分が指定されている場合、③特別受益者がいて受益証明書を添付し、残りの相続人については法定相続分で行う場合、④判決(裁判上の和解を含みます)による場合を除いては、分割協議書は必要になります。
①の場合には相続人が多いと、共有者が多くその後の処分が大変になります。
②の場合は、公正証書遺言を除いて家庭裁判所の検認手続きが必要です。
③の場合は、被相続人から生前あるいは遺言により財産的利益を得ており、自分の相続分は無いとする証明書を受益者から取り付ける必要があります。(印鑑証明書付)
④の場合はかなりこじれている場合でしょう。
通常の場合は分割協議書を作成し、行います。
その方が後々問題も起きないようです。

破産管財人の資格証明書
2012.04.23
破産者の物件を売却する場合、移転登記の手続きは、破産管財人が行う事になります。(管財人が選任されている場合)
この場合注意しなければならないのは、添付すべき資格証明書です。
添付書面中、管財人の印鑑証明書は発行日から3か月以内である必要はありません。ところが資格証明書は、3か月以内の期間制限があります。
裁判所発行の印鑑証明書は、資格証明書と一緒になっている事が多いので、注意を要します。

取締役就任時の印鑑証明書
2012.04.10
商業登記において、取締役に就任する人物の印鑑証明書(個人が市町村長に登録したもの)の添付が求められるのはどのような場合かとの質問を、頂きました。
株式会社において、取締役会を設置している場合には、代表取締役に新たに選任された方だけが必要です。
取締役会を、設置していない会社の場合は、新しく取締役に就任する方全ての印鑑証明書が必要になります。
これは取締役会を設置していない会社では、取締役個々が代表権を有しているのが原則だからだと、説明されています。

被災者向け免許税免除 2
2012.02.14
以前説明した被災者向けの代替建物取得時の登録免許税免除について、先日仙台法務局の説明会で、一部弾力的な運用について情報提供がありました。
従来AB共有建物が罹災した場合でも、Bについて罹災証明がなければ罹災証明を提出したAのみが免除され、Bについては課税されていました。
しかし共有建物であれば罹災した事実は登記事項証明書を見れば、判明するはずです。
罹災証明書を世帯主についてのみおこなっている等特段の事情があれば、上申書と登記事項証明を添付することにより、免除の対象とする事もあるとの説明でした。

瑕疵担保責任条項
2012.02.07
売買による移転登記の時、瑕疵担保責任についての質問を受けました。
瑕疵とは見えない傷の事をいいます。不動産でいえば所有者が気づいていないシロアリの被害などをいいます。
通常の注意をしても気づかないもので、本来有しているべき品質を有していなかった場合に契約の解除や、損害賠償が認められます。
問題なのは、最近の売買においてはこの瑕疵担保を排除する条項が定められていることが多いことです。
排除されていれば、売主が知っていた場合以外、責任を追及できません。
排除されていなくても、瑕疵担保責任を負う期間は3ヶ月程度とされていることが多いようです。
契約時には注意することが必要です。

1年間ありがとうございました。
2011.12.28
今年も無事1年間の仕事を、終えることができました。
これもひとえに皆様のおかげです。ありがとうございました。
当事務所は、12月29日から1月3日までお休みをいただきます。お急ぎの場合は、司法書士の携帯(090−2844−7764)まで、ご連絡をいただければ幸いです。
来年が、皆様にとって喜びの多い、笑顔の1年となりますことを、お祈りいたしております。
ありがとうございました。

登録免許税の被災地軽減措置について
2011.12.16
12月15日から東日本大震災の被災者については、登録免許税の軽減措置が新たにとられています。
課税標準に一定の調整率をかけて、税負担を軽減しています。
すでに納付した方についても、3月にさかのぼり計算し、還付措置がとられます。詳細は法務局HP以下のアドレスをご覧ください。http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyouseiwariai_index.html
仙台市でいえばおおむね15%程度軽減されています。

一時使用賃貸借
2011.12.13
先日仮設住宅用地を賃貸するので、賃貸借契約書を作成して欲しいとの要請を受け、公正証書にて作成いたしました。
この場合に作成したのは一時使用賃貸借契約書というものです。
これは借地借家法25条に規定されているもので、借主が一時的に建物所有のために借りる場合であって、借地権の長期間存続を必要としない場合に、借地権の存続期間、建物買い取り請求権等の規定が適用されないとするものです。
よく利用されるのは、選挙事務所、作業員宿舎等などを設置する場合です。
文言だけを一時使用とするだけでは不十分で、土地の使用目的、期間、建物の種類等を明記し、一時使用とする客観的かつ合理的な理由が存在することが必要です。

虚無名義人の登記
2011.11.28
先日、お客様から個人名での抵当権の設定を依頼されました。そのときに
抵当権者となる方から、印鑑証明もしくは住民票は必要ないのか?との質問を頂戴しました。
結論から申しあげますと、不要なのです。
個人の方が所有権を取得する場合は、虚無名義人の登記を防止する為住民票等の添付が必要となります。
しかし抵当権の設定には抵当権者の住民票等の添付を義務づける規定がないのです。
昔受験時代に読んだ解説書には、要求する条文がないからという変な解説がついていました。
もちろん我々司法書士が登記をする場合には、本人確認書面等で確認し、
虚無名義の登記などは発生させないようにいたします。
しかし、本人申請の場合にはどうでしょう・・・・・
住民票の添付は求めるようにするべきではないでしょうか。

バイヤーズエージェント
2011.11.17
日本の不動産業界は仲介において、売り主、買い主双方と媒介契約を結ぶことがあります。(これを業界用語で両手といいます。)この場合売り主、買い主の双方から手数料を受け取れるわけです。
これに対して、アメリカにおいては双方の仲介人となることはありません。売り主側であれば、売り主の為だけに働くわけです。
民主党が政権交代を目指したときに、日本においても双方の仲介人となることは、今後廃止しようという動きがありました。(その記事が出た日に大手不動産会社の株価が軒並み値下がりしました。)利益相反行為ではないかというのが理由です。
一部の評論家の中には、今後不動産の購入希望者は、自分の為に物件を探し交渉してくれるバイヤーズエージェントを選び、そのエージェントに購入を依頼するようになるべきだと説きます。
このことは確かに購入者にとっては良いことだと思われます。
信頼できるエージェントに依頼すれば、安心感は大きいからです。
しかし、不動産を探す方はどうしても物件中心に探すため、その物件を押えている業者さんに依頼するようです。
物件を見つけてから、信頼する業者さんに買い付けを入れてもらうのも一つの方法かもしれません。

後見人について
2011.10.27
今月、続けて二人の方の成年後見人に選任されました。いずれも前任者がいたのですが、財産管理内容が不透明ということで私が後任に選任されました。
どちらの前任者も、帳簿をつけておらず、支出が何に使用されたのか不透明なものでした。
時間が経過してしまうと人間の記憶は曖昧になるものです。しっかりと記録をつけ、明確な管理を心がけようと改めて思わされました。

意思表示ができない場合の登記
2011.09.19
先日、父親の相続手続きをしたいのだが、母親が認知症なのでどうしたらよいのか?との質問をいただきました。
意思表示をすることができなければ、遺産分割の協議はできません。
このような場合、法定相続分で登記する方法があります。相続登記は保存行為として相続人の1人から申請することができるからです。但し申請人以外については、登記識別情報通知が発行されませんからそのことは注意する必要があります。
上記手続の場合には、受益証明を添付した相続登記を申請する場合も含まれますので、相続を希望しない相続人を除いて登記することもできます。
受益証明はよく相続放棄と混同されますが、相続放棄がマイナス財産を含めた全面放棄で家庭裁判所での手続きが必要であるのに対して、受益証明はプラスの相続分がないとする申述で、登記用に印鑑証明書を添付して当該相続人が作成すれば足ります。

事前通知について
2011.09.12
不動産会社の方から、登記済証がない場合に本人確認情報以外の方法がないかとのご質問を受けました。
登記済証、登記識別情報が無い場合、申請代理人が本人確認情報を作成して登記するのが一般的な方法です。
しかし方法としては事前通知による方法もあります。
これは、登記申請がなされた場合、登記済証・本人確認情報とも添付されていない場合、本人限定受取郵便で申請人に対して通知をし、当該通知に対して申請内容が真実である旨の申し出があった場合に登記申請を受け付けるというものです。
事前通知は、同時決済が原則の売買にはなじみにくいものと思われます。
不動産会社の方にも、本人確認情報の活用をおすすめいたしました。

夏期休暇について
2011.08.10
8月13日から8月16日まで当事務所は、夏期休暇とさせていただきます。ご迷惑を、おかけいたします。お急ぎのご用件は、司法書士の携帯電話(090−2844−7764)までご連絡を、お願いいたします。

受益証明
2011.07.28
先日、相続登記の相談時に、別の物件を登記したときに、兄弟は放棄しているとのお話しがありました。しかしよくお話を聞くと、相続発生後二年後に放棄したというのです。
相続放棄は、自己のために相続が発生したことを知りたる時より、三ヶ月以内に行う必要があります。(もっとも財産関係を調査するために延長することはできます。)
おそらくこの場合は特別受益証明を添付しての相続登記ではないかと思われます。これは、被相続人が生前に相続人に対して、生活の援助等で相続分以上の財産的援助を行っていた場合に、そのことを相続人が証明し、相続分がないとして登記手続きをおこなうものです。
相続放棄と異なり、マイナスの資産は承継することとなります。

被災企業並びに被災企業取引支援施策研修会(東日本大震災支援事業)について
2011.07.02
8月9日に、上記研修会にて講師をつとめさせていただくことになりました。当日は債権回収の方法、金融機関との対応方法、借地、借家についての震災における問題点などについて説明をしたいと思っています。
主催は法人会で、場所は仙台市青葉区大町1-1-30 新仙台ビルディング6階です。開始時間は13時30分です。
研修会の後、個別の相談会も予定されています。私のほかに、公認会計士の椎木先生、社会保険労務士の高山先生がそれぞれの専門分野について、講習を行います。
ぜひおいでくださいますよう、ご案内申し上げます。

被後見人の不動産売却
2011.06.26
高齢者で認知症の方の不動産売却について、どうしたらよいかとの相談が、よくあります。
有効な意思表示ができない以上、法律行為である売買契約はできません。
そこで親族の方が、後見人を選任して売却してほしいというケースが、多いようです。
その場合注意しなければならないのは、後見の制度は被後見人等の利益のためにある制度だということです。
たとえば、被後見人が今後老人ホームで生活してゆくための売却であればかまわないでしょうが、親族が借入金を返済するための売却などは許されないこととなるでしょう。
又、仮に被後見人の利益であっても、被後見人の自宅の売却については家庭裁判所の許可が必要となります。
後見人選任の可否、不動産売却の可能性等については事前に慎重な検討が必要と考えます。

賃貸借契約の中途解約について
2011.06.11
賃借人が中途で賃貸借契約を解除した場合の違約金について質問を受けました。
その事案では、契約してから1年以内の解約について、月額賃料の3分の2あまりの違約金が定められていました。
賃貸借契約を中途で解約されますと、賃貸人は新たな借主を、さがさなければなりません。賃貸借の需要は3月から4月にピークを迎えます。たとえば5月に解約された場合、下手をするとその後11か月間空き家となる可能性もあります。
そのような理由から、1か月から3か月分程度の違約金は合理的とする判例が多いようです。
相談された事案については、違約金はやむ得ないものと思われます。
ただし、その金額があまりに大きい場合には、両者のバランスを考え、一部は免除されることもあります。

被災者向け免許税免除
2011.06.03
以前ご紹介した、登録免許税の被災者向け免除処置ですが、当初は代替建物と被災建物の所有者が全く同一でなければならないとの、法務局の見解でした。
ところが先日被災建物がAさんの所有、代替建物がAさん、Bさんの共有である場合でも、Aさんの持分相当額については免除を認めるとの見解が明らかにされました。
国難ともいうべき情勢ですから、良い措置だと思われます。
免除を受けるためには、被災建物、敷地の登記事項証明書、り災証明書(住居表示が実施されている地域では、地番と住居表示の表示があるもの)
が必要となります。

登記事項証明書等の手数料免除
2011.05.22
前回東日本大震災の被災者について、登録免許税が免除されるという情報を、お知らせいたしましたが、今度は登記事項証明書等の発行手数料が免除されるという情報です。
登録免許税の免除と同じように、被災者が罹災証明等を添付して、被災建物、被災建物の敷地、代替建物、代替建物の敷地について登記事項証明書、建物図面等を請求する場合、交付手数料(登記事項証明書の場合1通700円)が免除されます。
注意が必要なのは、オンラインで申請する場合適用がないということです。

被災者向け免税措置
2011.05.08
4月28日から、東日本大震災の被災者が代替建物を取得した場合の、登録免許税免税措置がスタートしました。
具体的には、被災者が代替建物を取得した場合の、保存登記・移転登記・抵当権設定登記の免許税が免除されるものです。
土地についても、被災代替建物の敷地とされるものであれば、面積が被災建物の敷地面積を越えない範囲は、免税措置が取られます。(細かな要件があります。詳細は司法書士にお問い合わせください)
注意しなければならないのは、抵当権設定については、ローンが根抵当権の場合は対象とならず、所有権移転登記等と連続して設定登記を申請しないと、免税対象とならない点です。
個人のみならず、法人も対象となります。
また、被災建物所有者の相続人も対象となります。
平成33年3月31日までに登記を受けるものが対象となります。

地震が原因となった損害について
2011.04.10
あるビルのオーナーから、地震の影響で外壁が隣の駐車場に落ち、駐車していた車を傷つけてしまったのだが弁償しなければならないのか?との質問を受けました。
民法717条は土地工作物の所有者に無過失責任を規定しています。しかし今回の震災のような予期できない外力によって事故が発生した場合にまでこれを適用すると、瑕疵ある工作物を支配する以上重い責任を負担させるべきとする法の趣旨から外れてしまいます。
前回の宮城県沖地震におけるブロック塀倒壊事例においても、仙台地方裁判所は安全性について「当該工作物の通常備えるべきいわゆる相対的な安全性をいう」としており、通常の地震に耐えうる程度の強度があったのであれば、損害を賠償する必要はないものと思われます。(なお上記判例は、築造された当時の基準に照らした安全性で足りるともしております。)

破産手続きと不動産 2
2011.03.26
前回、不動産を所有していても同時廃止が可能である場合として、不動産の価値より、設定されている担保権の残高がかなり大きい場合があると書きました。
裁判所は、その判断の資料として通常不動産会社の査定書を、添付させます。仙台地裁の場合ですと通常2通(もちろん異なる会社のもの)程度要求します。
予納金の金額が大きく異なるわけですから、できる限り同時廃止にするよう査定書を添付していますが、一部の不動産会社では、売却可能金額をかなり高く記載する場合もあり、3社くらいに依頼することもあります。

破産手続きと不動産 1
2011.03.21
不動産を所有している場合に、破産手続きが可能か?との質問がありました。
破産原因は「支払不能」「支払停止」「債務超過」の3つが規定されています。資産として不動産を所有していても、換価が困難であれば、支払不能、支払停止、債務超過はあり得ますので、破産となるわけです。
ただし不動産等の財産がある場合、手続き上「同時廃止」とはならず、
「管財事件」となるわけです。
管財事件になりますと、管財人が選任され、財産を換価し債権者へ配当することとなります。管財事件では予納金が求められ、少なくても30万程度を申し立て時に予納することとなります。(同時廃止の場合は1万円強)
ただし不動産を所有していても不動産の価値が、当該不動産に設定されている担保権の残高よりかなり少ない場合は、同時廃止が認められることもあります。

地震のもたらす影響 住宅ローン
2011.03.19
今回の地震で、多くの方が家を失いました。
そのため、住宅ローンがどうなるのかとの質問をいくつか受けましたので、そのことについて説明してみます。
住宅ローンは、金銭消費貸借契約というもので、その目的である住宅が滅失しても金銭の返還義務は残ります。
被災し住むところを失ったうえ、ローンだけは残るということになります。保険では、地震保険に加入していなければ保険金は支払われません。また保険金でローンを完済できる方は少ないものと思われます。
政府はおそらく返済猶予策を、打ち出すものと思われます。
被災者のために素早い対策を期待したいものです。
現在債務整理等により任意弁済中の方は、債権者に事情を説明すれば、通常の生活に復帰するまでは猶予をしてくれるものと思われます。

地震お見舞い
2011.03.15
地震にて被災されました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
小職も地震発生時、東北新幹線に乗車しており、車内に11時間あまり閉じ込められました。幸いJR東日本の皆様のすばやい救出作業のおかげで、助かりました。JRの皆様には深く感謝いたします。
大変な災害ですが、力を合わせて乗り越えてゆければと思っております。
被災者の皆様の、1日も早い救出、復興をお祈りいたします。

任意整理と個人再生
2011.03.05
債務整理の場合、一番悩むのが任意整理でゆくべきか、個人再生手続きあるいは、破産手続きをとるべきかという点です。
通常所得と債務総額を、比較のうえ決定しますが、ご相談におみえになる方の多くは破産を避けたいとのご意向です。
所得にもよりますが、消費者金融系の借入総額が200万(利息制限法による引き直し計算後)を超える場合、任意整理はかなり厳しくなります。
個人民事再生手続きは、手続きとしては煩瑣ですが、債務額を最大5分の1まで圧縮することが可能ですので、破産を避けたい方にはお勧めの方法です。破産を考える前に検討してみてはいかがでしょうか?

遺言執行者
2011.02.19
先月、特定遺贈のために遺言公正証書の作成を、依頼されました。
特定遺贈というのは、自分がなくなった場合に特定の不動産、債券などを与えることを言います。(これに対して相続財産のすべて、あるいは一定割合を与えるものを、包括遺贈といいます。)
第3者(推定相続人以外という意味)への遺贈の場合、相続人とのトラブルが予想されます。
問題となるのは、不動産を遺贈する場合、登記手続きの義務者が相続人となることです。自分が相続できると思っていた資産を第3者にとられ、しかもその手続きに協力するするのは、だれでもいやでしょう。通常協力を得られる場合は少なく、裁判になることさえあります。
そのため、第3者に遺贈する場合には、遺言執行者を定めておき、遺言執行者が受遺者と共に登記等の手続きをするよう定めておくべきです。
今回の特定遺贈については、私が遺言執行者となることにいたしました。

貸金業取扱主任者
2011.02.05
昨年、貸金業取扱主任者試験を受験しました。債務整理事件にかかわる以上、理解しておくことが必要かと思い勉強してみました。
かっての、業界が主導していた時のものに比べて、かなり内容的には良くなっているように思いました。試験内容は、貸金業に関する規制が多く、勉強になるものでした。
できれば、もう少し民法、民事訴訟法などを盛りこめば業者の方のレベルも向上するのではないかと感じました。
久しぶりの試験でしたが、先日無事合格通知は届きました。

アルバイトさん募集
2011.01.26
事務のお手伝いを、お願いできる方を探しています。
一時間800円で、時間は9時から16時まで、(時間についてはご相談に応じます。)パソコンの操作ができればOkです。
司法書士事務所の経験は無くともOKです。
2月15日くらいからお願いできれば助かります。
問い合わせはHPの問い合わせからでも、お電話でも結構です。

区画整理組合の登記
2010.12.31
区画整理組合が行う登記といえば、通常は本換地処分に伴うものです。
ところが今月、区画整理組合が登記権利者(所有権を取得する登記)となる登記手続きを、行いました。
法務局とも事前に相談いたしましたが、権利者となる登記はみたことがない、との回答でした。内議していただいたところ、区画整理地内の不動産であればかまわないとのことでした。
区画整理法で、区画整理組合は法人であると規定されておりますので、登記が可能なのは当然ともいえます。事業地内に限るというのはおそらく、組合の設立目的から、事業地内以外の不動産を取得することは、法人の権利能力の範囲外と考えたのではないかと思います。
なおこの場合に添付すべき書面は、都道府県知事が発行する資格証明書となります。(政令指定都市の場合は、市長{地方自治法、同法施行令で権限が委譲されています}の発行するものとなります。)

相続登記」の必要性
2010.12.23
銀行の方からの紹介で、相続登記の依頼が」ありました。そのときご質問をいただいたのが、相続の登記はもう少し後でもよいのではないかということでした。登記自体は第三者に対する対抗要件ですので、5年後、10年後でもかまわないのです。問題は10年経過すれば、相続する権利を持っていた方が亡くなり、当事者同士言葉を交わしたことのない方と、交渉しなければならない、ということです。自分の知っている親戚あれば、相続の承認を簡単にしてもらえます。しかし叔父さん、叔母さんの子供が相続の権利を持った場合はいかがでしょうか。早めの手続きはトラブル防止のためには欠かせないことだと思います。

敷金返還請求
2010.11.28
今月は敷金の返還請求だけで、4件のご相談がありました。
このうち3件は、提訴することなく、交渉だけで返還が終了いたしました。
提訴したとしても、国土交通省の示すガイドラインは、賃借人を保護する形で規定されていますので、よほどひどい使い方をしていない限り、ある程度の返還は期待できます。
それにしても、敷金を全く返還しないで、むしろ原状回復費用を請求する大家さんがいるのには、驚きます。

商号
2010.11.04
会社を設立する場合、商号を定める必要があります。通常設立の相談においでになる方は、商号を決めてからおいでになります。
先日中小企業診断士の先生から、商号の見方、望ましい付け方を教えていただきましたので、参考までに記載してみます。
個人の名前や、名字を商号に入れる方は、一般的に自己顕示欲が強く、ワンマン経営者となることが多いそうです。
商号は、商売の目的や性質がわかるようにするのが良いそうです。できれば経営理念等がわかれば、ベターだそうです。
素早い対応を売りにするのであれば、スピードとかクイック等の文字を入れるようにするわけです。
ちなみに私の事務所は自分の名前ですが、これは自分の名前以外にすると、司法書士会から理由等の説明を求められ面倒なので、自分の名前にしただけです。もう少し考えれば良かったと反省しています。

住宅瑕疵担保責任保険法
2010.10.09
昨年10月から新築住宅については、業者に対して瑕疵担保責任を確実に履行させる為に、保険加入あるいは保証金供託が義務付けられています。
瑕疵担保とは通常の注意をしても発見できないような欠陥をいいます。つまり欠陥があって修理しなければならないのに、業者が倒産等の理由で修理代金を支払えないような場合に、購入者が損害を受けないよう法律で、保険加入等を義務付けたのです。
業者が支払い不能の場合、購入者は直接保険会社に請求することができます。
実はこの制度、新築については強制ですが、中古住宅についても保険制度が今年の春からスタートしました。
加入するのは販売業者ですが、保護されるのは購入者です。
中古住宅を購入する場合には、業者さんに保険加入の有無を確認し、加入を要請してみてはいかがでしょうか?

TMK
2010.09.11
東京で仕事をしていたときの仲間から、TMKを購入したいとの相談を、受けました。TMKとは特定目的会社の略称です。資産の流動化に関する法律に基づき設立された会社をいいます。依頼者がTMKを購入(つまりは会社を買い取る)したいというのは、TMKの保有する不動産を購入したいからです。
通常不動産を現物(信託受益権等ではなく)で購入する場合、登録免許税、不動産取得税等のコストがかかります。会社ごと買い取れば、そのコストは発生しません。
しかし、会社を買う場合、その会社の資産のみではなく、当然負債も承継します。
一般の会社であれば、どの程度の負債があるのかクリアではありませんから、やめるようにすすめます。
ところが、TMKの場合特定資産を流動化する以外の業務は禁止されていますので、理論上は債務、資産は明確になっているといえます。
TMKはただのヴィークルに過ぎないため、実際の業務はすべて委託しており、社債等の発行もあり法律関係は複雑です。
大変な仕事になりそうですが、弁護士、公認会計士の先生と協力して取り組んでみたいと思っています。

相続のホームページ
2010.08.22
この度、弁護士の村上敏郎、匠両先生と公認会計士椎木秀行先生と共に、
相続相談専門のホームページを作成致しました。
これまでの相続相談に関するHPは、特定の士業についてのものが多く、ワンストップですべてを解決できるものが少ないように感じていました。
今回のHPは、経験豊富な先生方の協力により、お客様の悩みを一度に解決できる場所になっているものと、自負致しております。
是非とも一度御覧いただき、ご意見をいただければ幸甚です。
URLは、http://www.sen-no-souzoku.com/です。

清算価値保障原則
2010.08.15
個人民事再生を申し立てる場合、最低弁済額を算出します。通常は債務総額の5分の1(債務額により変動あり、もっとも依頼が多い債務総額500万以上1500万未満の場合の例)と説明しています。
この他に、給与所得者等再生であれば可処分所得による返済基準と清算価値保障原則による基準があり、このうち最も高いものが、弁済計画による返済額となります。
可処分所得によるものとは、収入から公租公課、及び政令で定められた金額(生活保護を基準としており、地域により異なります。)を差し引いた金額の2年分です。目安としては年収500万くらいで200万前後になることが多いようです。
清算価値保障原則とは、破産した場合の相当額は最低支払わなければならないというものです。不動産、車などがあればそれらを売却した場合の価格。生命保険などに加入していれば、解約返戻金相当額。預金、現金などを合算した金額です。債権者に破産時よりは多くの弁済を受けさせる為に必要となります。
小規模個人再生では可処分所得による基準は適用されませんが、清算価値保障原則は適用されます。

妥当な結論
2010.08.01
先日、不動産の帰属紛争について相談を受けたときのことです。相談者の方が「自分は正しいのに、なぜ裁判所は認めてくれないのか?」と嘆いておられました。当該事案は、弁護士の先生も双方についている複雑な事案ですので、ここで紹介するのは避けますが、本人の話を聞く限りは確かに正義は相談者の方にありそうでした。
そこでご説明したのですが、民事訴訟は絶対的な正義を追及するものでは無いということです。
刑事訴訟は、真実の追究を使命としています。しかし市民間の争いを解決する民事訴訟では、真実の追究よりも結論の妥当性が重視されるのです。
そのため、時間の経過や現在の事実状態を優先して判断がなされることも、多いのです。
もっとも当事者の一方にとっては、妥当とは思えない場合も多いとは思いますが・・・・・・。

買い戻し特約と売買予約
2010.07.06
先日、お客様から「自宅を担保にお金を借り入れる為、自宅の所有権を第3者に移転することにした。3年後に間違いなく取り戻す方法はないのか?」との質問を頂きました。
この場合考えられるのは、買い戻し特約の登記か、再売買の予約による所有権移転仮登記ということになります。
買い戻し特約は、第3者へ移転登記すると同時に、付記登記で行うもので、売買代金と費用が登記事項となり、原則売買代金と費用を支払えば所有権を取り戻せることになります。
再売買の予約は、数年後に売買代金を支払って所有権を取り戻すものです。売買代金が最初の売買より高額になることもあり得ます。(金利・元本の合計額ですから通常高くなります)
買い戻し特約は期間制限が有り、最長10年ですが、再売買の予約には期間の制限はありません。債権者の立場であれば再売買の予約の方が、使いやすいといえます。
今回の依頼者は、債務者側でしたので買い戻し特約を、お勧め致しました。

養子縁組の必要性
2010.06.08
先日ホームページをみられて、法律相談に訪れた方の話です。
その方は、祖父とずっと同居されており、祖父が亡くなったので、その不動産の相続手続きをしたいとのご相談でした。
ところが、その方のお母様はご存命で、親子仲が良好とはいえず、連絡を取っていないとのことでした。
賢明な皆様はすでにお気づきのことでしょうが、この場合相続権があるのはお母様です。(ちなみに他に相続人はいませんでした。)
ご相談においでいただいた方は、相続財産に対しては何らの権利もありません。
このような場合に備えて、遺言をしてもらう方法もありますが、遺言する方も自分の死亡が前提ですのであまり良い気はしないでしょう。
できれば養子縁組をして、相続する権利だけでも確保しておかれた方が良いでしょう。

本人確認情報
2010.05.22
先日、お世話になっている銀行の方から、「抹消登記にあたり登記済証がない場合、法人の代表者に対して本人確認が必要なのですか?」という質問をいただきました。
決済の前日に登記済証がないということで、大騒ぎになったとのことでした。
登記済証、登記識別情報を添付できない場合、原則としては事前通知がなされます。但し司法書士等が、本人に間違いないという書面(本人確認情報といいます)を添付した場合は、印鑑証明書を添付すれば事前通知を、省略することができます。
この場合法人で確認すべき本人とは、法人の代表者若しくはこれに代わるもの者とされています。代わる者とは支店長、部長等その業務権限がある人物です。
頭書の質問には、業務権限を有する方の確認ができれば大丈夫ですと、お答えいたしました。

相続直後の預金払い出し
2010.05.06
被相続人が死亡した場合、預金はどうなるのですか?
こんな質問をいただきました。
預金は銀行に対する債権ですので、遺産分割の協議をしない限り法定相続分にしたがって相続人が取得します。(遺言があれば、それにしたがいます。)
この場合問題となるのが、手続きです。
銀行によりその対応方法はまちまちですが、各相続人が単独で預金を引き出すことは、難しいようです。(一部認めている銀行もあるようです。)
相続人全員で請求するか、遺産分割の協議書、調停調書を添付して請求するのが一般的です。
その他に相続人を特定する資料として、戸籍謄本、改正原戸籍謄本など相続登記申請と同じレベルの書面の添付が求められます。
要求される書面も、銀行により異なります。
できれば葬儀費用等、すぐに必要となるお金は、相続人全員で拠出するか、預金凍結前に払い出しておくべきでしょう。

保証書
2010.04.10
先日売買にあたり、「権利証がないので保証書を、お願いします。」というご依頼がありました。
平成17年に改正不動産登記法が施行され、現在保証書の制度は廃止されています。
登記済証がない場合、①事前通知の方法、②資格者による本人確認情報の提供、③公正証書を利用する方法、のうちいずれかの方法を利用することになります。
おそらく保証書といわれた方は、本人確認情報の提供のこととして、お話しをされたのかと思います。
本人確認情報を提供する場合、登記済証を提供できない正当な事由のあることが必要です。
そして資格者は申請人と面談することが必要とされ、虚偽の情報を提供した場合には、刑事罰(2年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に処せられます。(法160条)

抵当権と根抵当権
2010.04.08
先月、お取引のある信用金庫の役員の方から、債務者が死亡して1年経過しているので債権が確定しているのではないか?との質問を受けました。
内容をお聞きしてみると、担保権は抵当権とのことでした。
抵当権は根抵当権と異なり、確定という概念はなく、債務は相続人に承継されますので、抵当権の変更手続きをとられるようアドバイスを致しました。
根抵当権であれば、債務者が死亡して6ヶ月を経過してしまえば、債権額が確定し、以後発生する債権は担保されません。
字が一字違うだけで手続きの内容は大きく異なります。

リスケ
2010.03.20
2週間ほど前、ホームページからの問い合わせで、住宅ローンの支払が厳しいので、売却をするべきかとのご相談をいただきました。
現在、銀行はローン返済についての相談にできるだけ応じるように、金融庁から指導を受けています。
そのため、返済方法の変更についても1〜2年前とはまったく違う対応をしており、できる限り応じる方向で検討しているようです。
ご相談いただいたお客様には、とりあえず銀行に相談し、返済方法を変えていただいてはとアドバイスをさせていただきました。
現在個人再生手続きを、受任しているお客様も返済方法の変更が認められています。
債権者に相談するのは気が引けるものですが、焦って結論を出す前に相談してみるのも一つの方法です。

登記識別情報通知
2010.03.06
先日、売買決済の直前に権利証がないと、銀行の方からお電話をいただきました。よく聞いてみると、売買対象の不動産を取得したのが、平成18年の1月だというのです。仙台法務局本局管内では、平成17年11月28日から、オンライン指定されため、登記済証(一般に権利証といわれているのは、所有権を取得した際に発行される登記済証のことです。)は発行されず、登記識別情報通知が発行されています。
厚い紙の権利証ではなく、薄いグリーンの紙を探して欲しいと依頼したところ、無事に発見していただき、事なきを得ました。
登記識別情報通知は、権利を取得した場合に法務局から発行されます。
かっての登記済証に比べると、薄く見落としやすいのかもしれません。

公図
2010.02.08
先日、銀行の方から公図について質問をいただきました。どうして実際の所在と異なっているのか?ということでした。
公図は昔の土地台帳などを基に作成されているため、現実の所在とは大きく異なることが多いのです。
国土調査などを経ている場合は、かなり正確ですが、担保とする場合などは、実際に現場を確認することが必要です。
札幌など、公図が存在しない地域もあります。

遺産分割協議書に添付する印鑑証明
2010.01.27
登記の申請に、印鑑証明書添付はセットのようなものです。
よく質問を受けるのが、分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期間についてです。
通常登記義務者(売主、抵当権を設定する担保提供者等の方を言います)の添付する印鑑証明書は発行から3ヶ月以内とされています。
ところが遺産分割協議書(相続登記に添付することが多い書面です。)に添付する印鑑証明書についてはこの期間制限はありません。
なぜでしょう?
分割協議は必ずしも登記のためのみにおこなうものではなく、相続税申告のためなどにおこなって、登記が未了のまま放置され、その後売却することになった時点等で登記することが実際は多いといえます。
つまり実体としての権利変動が発生した時点での、変動の事実を証するものである以上、その当時の印鑑証明で良いという考え方なのです。

民事紛争の解決
2010.01.06
民事の紛争で当事者の方が主張されるのは、「自分は正しいのだからすべて認められ、且つ権利はすべて実現されるべきだ」ということです。
論理的には正しいくとも、証拠がなければ訴訟に敗れることはあります。
又、訴訟に勝ったとしても、何もない人間には強制執行の行使方法がありません。
当事者が正しいと考えていても、法律の世界では認められないことも多くあります。
当事務所では、依頼者の方が一番有利になるような方法を提案しています。
相手方が納得して支払ってくれる和解は、そういった意味でもっとも有効な方法と言えます。
裁判所でもあらゆる段階で和解を勧めるのは、当事者が納得して支払う方法が一番履行の確立が高いからです。
自分が一歩引くことが解決への近道となることもあります。一度考えてみてはいかがでしょうか?

一年間ありがとうございました
2009.12.31
今日今年一年が終わります。
皆様のおかげで今年一年も良い年でした。
今年から、ホームページを開設致しましたが、多くの方々にみていただいたことは、喜びのかぎりです。
来年も皆様のお力になれるよう頑張ってゆきたいと思います。一年間ありがとうございました。
来年が皆様にとって良い年でありますことを、心よりお祈り致しております。

事務所移転
2009.12.21
来年から事務所を青葉区本町へ移転いたします。
一階にファミリーマートが入っているビルの7階になります。
仙台駅に近く、皆様にとってもご利用しやすくなると思います。
お近くにおいでの際は、どうぞお立ち寄り下さい。

過払い金返還請求訴訟ーA社の答弁書
2009.11.29
過払い金返還請求訴訟における金融会社A社の答弁書が傑作でしたので、お伝えしたいと思います。
いろいろと反論を記載しているのですが、中でもおもしろいのは税金を支払っているので、過払い金(不当利得)で返還すべき分は、過払い金のうち55%だけだというものでした。
税金で支払ったものは、修正申告して返還請求すべきものであり、不当利得とは別の議論だと思うのですが・・・・・。
いずれにせよ、いろいろな考え方があるものだと考えさせられました。
ちなみにA社の答弁書、準備書面はすべてパターン化されており、当方の訴状、準備書面の内容は読んでさえいないようです。
裁判官からも注意されていたようですが、いつまで続けるつもりなのでしょうか?
ADRを申し立てしているようですが、もう少し誠実な対応をとるべきではないでしょうか?

取締役の任期
2009.11.15
先日ある方から、役員変更登記を2年に一度しなければならないのが大変だというご相談を受けました。
旧商法では取締役の任期は2年を超えることはできないとされており、経営者の方にとって大変手間のかかる問題でした。
しかし改正された会社法では、株式の譲渡制限を設けている会社については、定款で定めることにより最長選任後10年以内の、最終の決算期に関する定時株主総会終結の時まで伸長できるとされています。(会社法332条2項 委員会設置会社を除く)
ご相談者の方の会社は、株式譲渡制限を設けており定款変更することにより、取締役の任期伸長が可能でした。
その事をお伝えしたところ、早速そのように変更をするとのことでした。
ここで残念なのは、その間に役員変更登記を受任した先生が、期間伸長についてアドバイスしなかったことです。
2年に一度の登記がなくなることは惜しい事かもしれません。しかしそれ以上にお客様にとって有利な方法をお伝えすることの方が、大切だと思うのですが・・・・・。

未成年後見監督人
2009.11.07
先月末、家庭裁判所から未成年後見監督人に選任するとの審判を受けました。ご両親がお亡くなりになり、小学生と中学生の兄弟が残され、叔父さんが後見するとの事案です。
かなりの資産があり、その管理、監督が主なミッションとなります。
現在おこなっている成年後見監督人とは手続きも異なり、戸惑う部分もありましたが、公益の為に仕事ができるということで、非常にうれしく思います。
新しい仕事ができるというのは、楽しいことだと改めて感じました。

金融業
2009.11.01
現在貸金業の改正にともない、多くの金融業者が廃業を検討しているようです。
先日の日本経済新聞でも業法の改正見直しについて報道されました。
そこで金融業というものは、はたして必要な業種なのか、今回は考えてみたいと思います。
そもそも金融というものは、事業を始める場合資金不足のものが、将来性を担保としてお金を調達する手段であったと思われます。
ところが、お金を貸すサイドは将来性よりも回収の確実性を重視し、とくに近年の消費者金融は利用者の無知と、日本人の従順性を利用して、単に収益を上げることばかりを重視してきたのではないかと思われます。
現在、過払い請求で司法バブルとよばれ、脱税などおこなう法律従事者にしても大同小異ではないでしょうか。
金融は私たちが人生を、生きてゆくために必要不可欠なものです。一部の人間が、自分たちの利益のためにもてあそんでいることに怒りを覚えます。
知識のみが優先し理念なき世界では、本来の金融の意味が失われているような気がします。
夢を持つ人間に必要なお金が循環する社会を創りあげたいものです。

投資用マンションについて
2009.10.12
私は前職で日本版サブプライムローンの販売、審査、契約に携わっていました。
そのローンを利用されるのは、もっぱら投資用マンションを購入しようとする方々でした。そこで今回は投資用マンションについて、感想を述べてみたいと思います。
ローンの申し込みに来られる方は、年収1000万前後の方が圧倒的に多かったと思います。
当時首都圏でワンルームの新築マンションを購入した場合、だいたい平均1800万ぐらいだったと記憶しています。これを30年ローン(金利3.8%として)で満額借りた場合、毎月83000円(端数省略、以下同じ)の支払いになります。
これに対して当該マンションを賃貸した場合得られる家賃は、月額8万から10万の間であったと思います。
上限で貸すことができたとして、月額1万7000円程度の収益です。
ところがこれは、金利が一定であるという前提であり、変動金利で1%金利があがれば、毎月の返済額は94000円になり、収益はほとんどなくなります。
区分所有の建物である以上当然管理費、修繕積立金もかかるわけであり、固定資産税等も含めて、年間で考えればマイナスになります。
もちろん将来において資産であるマンションは残ります。
しかし空室になればローンの返済は手元から捻出しなければなりませんし、あまり割の良い投資とは思えませんでした。
もっとも高額所得者にとっては、節税の効果が大きかったのかもしれません。

司法書士報酬について
2009.10.09
先日お客様から、司法書士の報酬について質問がありました。
その方は高齢の方で、お父様の相続登記を依頼したところ、30万ほどの報酬を請求されたというのです。
現在司法書士の報酬は自由化されており、各事務所でそれぞれに決めています。
司法書士会からは、以前適用されていた報酬基準に準じるように助言がなされており、私の事務所でもそのようにしています。
しかしながら、受任した事件によっては事前調査に時間を要したり、あるいは煩瑣な事務作業を要する場合があり、そのときにはその分を加算させていただいております。
登記事件であれば、不動産価格、債権額により報酬額が大体決まります。
但し、相続の場合には、戸籍による相続人の特定、相続人の意思確認等作業が多くなる可能性もあり、一概にどの程度の金額が適正とはいいがたいのです。
ご質問を受けたお客様には、担当された司法書士とよく話してみるようお伝えいたしました。

ミスコミニュケーション
2009.09.30
先日知り合いの不動産業者さんから、清算会社の登記が未了のため、売買決済ができずに困っているとのご相談をいただきました。
詳細にお話を聞いてみると、清算人の就任登記は終了しているのです。
清算人の印鑑証明と、資格証明を添付すれば移転登記は可能ですとお伝えすると、移転登記を行う先生が不動産の変更も必要だと主張しているというのです。
清算会社に表示変更登記が必要などという話は聞いたことがありませんし、これは何かの勘違いと思い、先方の先生に尋ねてみました。
その結果、司法書士が未了と考えていたのは、商業登記(清算)であり、不動産業者は不動産登記を考えていたということが、判明いたしました。
同じ言葉でも使う方によってその意味するところが違うようです。
良い勉強になりました。

支払督促
2009.09.17
前回は、少額訴訟について書きましたので、今回はもっと簡単に債務名義(強制執行ができる事を公証する書面)が取得できる、支払督促について説明してみます。
支払督促は、債権者の主張のみに基づいて、債務名義を取得させる事を目的とします。債権の存在に争いがない場合で、相手方が資金不足や感情的な理由で支払わない場合に活用すべき制度です。
債権者は、債務者の住所地を管轄する裁判所に支払督促の申立をおこないます。このとき請求債権額に対応した印紙を貼付しなければなりません、しかしその金額は、通常の訴訟の半額で済みます。又このとき郵便切手を1050円分添付します。
支払督促が相手に届けられて、2週間経過しても先方から異議の申立がない場合、仮執行宣言付与の申立をすることができます。
仮執行宣言が相手方に到達すると債務名義となり、強制執行する最初のステップが終了します。
支払督促は、債権者の一方的な言い分に基づくものですから、債務者が異議を述べますとその異議の範囲で失効します。
そして、支払督促申立のときに訴えの提起があったものとみなされ、通常の訴訟手続きに移行します。
現在裁判所では、支払督促を送付(裁判所の用語では送達といいます)するときには、異議の申出ができること、その方法等について記載して送付していますので、争いのある事案については、訴訟あるいは民事調停等を利用するべきでしょう。

少額訴訟
2009.08.24
家賃の回収依頼を受けました。回収するには少額訴訟が適当と判断し、提訴することに致しました。そこで今回は少額訴訟について説明してみます。
少額訴訟というのは、60万円以下の金銭の支払い請求を目的とする紛争について、1回の審理で終了させ直ちに判決を言渡す手続きです。
趣旨は、少額の紛争については、訴額に見合った経済的、時間的負担で、迅速に紛争を解決することにあります。
審理を迅速に処理する為に、反訴が禁止され、攻撃防御方法は第1回期日までにすべて提出しなければなりません。証拠についても即時に調べられるものに限定されます。(1回で結審するのですからあたりまえですよね。)
複雑な係争については、少額訴訟にはなじみませんので、職権で通常訴訟に移行させられることもあります。(民事訴訟法373条3項)
又、被告側からも、通常訴訟に移行するよう申述することができます。
少額訴訟の判決に対しては、送達を受けた日から2週間以内に、異議を申し立てることができます。
金融業者等が濫用しないよう、同一原告が同一の裁判所へ、年10回を超えて申し立てることはできません。
裁判所でも丁寧に説明してくれますので、紛争でお悩みの方は一度検討してみてはいかがでしょうか?

誠実な対応
2009.08.09
先月債務整理を依頼されたお客様が、債権者から提訴されました。
聞いてみると、支払いができないため債権者からの電話を、すべて無視していたとのことです。
請求してきた債権額はわずか18万円です。
債権者から電話があり、あまりに不誠実な対応のため提訴したとのことでした。(小職の受任通知が届く前日に申し立てしたということで、受任通知を発送した翌日に連絡がありました。)
債務をかかえている方の中には、債権者を回避される方が多いように思われます。債権者の従業員の方も業務として取り組んでいるのであり、誠実に対応すればあまり強硬な手段に出ることはありません。
人間として誠実な対応を心がけて欲しいものです。

本人確認について
2009.08.01
最近銀行、保険会社等で免許証等の提示を求められることが多いかと思います。銀行等金融機関は平成20年3月1日から施行された、犯罪収益移転防止法に基づき、特定取引においては本人確認が義務付けられたからです。
私たち司法書士も特定業者として、本人確認が義務付けられています。
犯罪収益移転防止法施行以前から、司法書士業界では本人の確認はかなり厳格に行われていました。
高額な不動産の移転登記等を行うわけですから、当然といえます。
お客様の中には、自分を信用しないのかと怒り出す方もいらっしゃいます。
そこで私が経験した、偽者を利用した借り入れについてお話してみます。
当時私は不動産担保融資を専門とする、金融会社の社員でした。
その申し込みは、女性の行政書士さんからの紹介でした。複数の借り入れを一本化するために、自宅を担保に1400万借り入れたいというものでした。申し込みには奥様のみがお見えになりました。
担保評価は十分でしたので、上司の決裁を得て契約することになりました。(その会社は大変慎重な会社で、契約してから中1日以上おかないと融資実行しません)
契約日に初めて所有者であるご主人さんとお会いしました。その会社の規定に従い免許証の提示を求めました。
ところが免許は取り消しになっており免許証を持っていないというのです。保険証のみでその場は契約を済ませました。
本人かどうかの確証をもてないため、その夜私はご自宅へ電話をかけました。ところが電話は通じないのです。(後で思えば電話線を抜いていたようです。)
そこで私は翌日の夜直接自宅を訪ねてみました。そこで、でてこられたのは、契約に来た人物とはまったくの別人であり、その方がご主人でした。
後で聞いた噂によると、紹介者がいろいろと知恵をつけていたようでした。
今から7年ほど前の偽者発見の顛末です。
私がその金融会社にいる間に見つけた偽者は、全部で6人だったと記憶しています。
人間、お金が絡めば大概のことはやってきます。
本人確認の重要性をご理解いただきたいものです。

貸金業法改正について
2009.07.26
最近の新聞でよく取り上げられていますが、貸金業者の数が3分の2になったといわれています。
貸金業法の改正により、利息の上限が引き下げられ、年収に対する貸付の上限が定められることが大きな原因といえます。
先日信用金庫の理事の方から「現在の不況下において改正は多くの零細事業者の資金調達する道を閉ざすものであり、行政の過剰介入ではないか?このようなことでは、闇金融を助長するだけではないでしょうか。」とのコメントをいただきました。
確かに欧米に比べ日本の金利は低く、新しい制限利率では貸金業者はリスクをとりづらいともいえます。
行政としては利率を下げるというような、経済活動に影響のある方法ではなく、借り入れに対する教育、啓蒙活動等に力を入れるべきではないかと考えさせられました。

類似商号について
2009.07.20
先日会社を作りたいという方からご相談をいただきました。
その方は会社の名称を、大手アパレルメーカーに似せて、お客様の信頼を得たいとのお考えでした。
現在の商業登記では、同一本店でない限り類似商号の登記は可能です。
しかし、他人の業務に係る商品表示、営業表示で、需要者に広く認識されているものと同一・類似の商品表示等を使用したり、混同させる行為は不正競争とされています。(不正競争防止法2条1項1号)
この場合損害賠償や差し止め請求を受ける可能性があります。
このことを説明しましたところ、ご理解いただき別の名称としていただくことになりました。
又、過去の裁判例では、まったく異なる業種(大手流通業者と貸金業者)でも損害賠償が認められています。
楽をして儲けようというのは、むづかしいようです。

相続財産管理人の所有権移転登記
2009.07.11
先日ご依頼があり、相続財産管理人の弁護士さんが不動産を売却する移転登記を行いました。
私の記憶では家庭裁判所に印鑑の届出をしておけば、その印鑑証明書を発行していただけ、その印鑑証明を添付すれば法務局も移転登記を受理していたようです。(どこの裁判所であったか記憶は定かではありません)
ところが、仙台家庭裁判所に問いあわせたところ、そのような届出は受け付けていないとの回答でした。
仕方なく弁護士さんの市町村に登録している印鑑証明書と、弁護士会の証明書(財産管理人は事務所住所で審判されているため、個人住所の印鑑証明では同一人と判断できないため)を添付していただきました。
弁護士の先生には、大変ご迷惑をおかけしてしまいました。職務としての売却ですから、印鑑の登録を認めていただきたいものです。
大変感じの良い先生でしたので助かりましたが、先生によってはかなりお叱りを受けるところでした。(今回はきれいな女性の弁護士さんでしたので、結構楽しい立会いでした)

借家の立ち退きについて
2009.07.04
先日不動産業者の方から、自分が所有している借家を取り壊して更地にし売却したい。ついては現在の入居者を立ち退かせて欲しいとの、ご依頼をいただきました。
私が驚いたのはプロである不動産業者の方が、借家人(賃料の延滞等はなく、誠実な賃借人でした)を自分の都合だけで立ち退かせることができると考えられていることでした。
建物の賃貸借契約は、期間の定めがない場合賃貸人の解約申し入れから6月を経過すると消滅します。(借地借家法27条第1項)
しかし賃貸人からの解約申し入れには正当事由が必要とされています。
この正当事由というのは、「賃貸人、賃借人双方の使用の必要性」を主たる判断基準とし、「賃貸借に関する従前の経過」、「建物の利用状況・現況」、「立ち退き料の提供」を総合的考慮して決定される。(同法28条)とされています。
通常相談されたようなケースでは、かなりの立ち退き料が必要となりますし、裁判になれば立ち退きを認められない場合もあります。
相談された事案では、業者の方は賃貸人が「壊すので退去して欲しい」といえば大丈夫だと考えられていたようです。かってはそれで退去していただいてたそうでした。当該事案では賃借人の方が弁護士さんに依頼されれば、かなりの立ち退き料が予想されます。(賃借人が高齢で、長期の賃借実績があり且つ賃料の延滞が一度もないetc)
借地借家法の規程は「建物の賃貸借」であれば、借家に限らず事業用の建物にも適用されますので注意が必要です。
それにしても「出てくれ」といえば出ていただけるというのは、東北という地域性なのでしょうか?

登記相談員
2009.07.02
昨日、法務局で登記相談員をおこないました。2回目の経験です。
この制度は法務局で本人申請をおこなう方に、申請書の記入方法をアドバイスするもので、法務局の要請を受け司法書士会が協力しているものです。
相談者は圧倒的に高齢者が多く、相談も相続登記に関するものでした。
できるだけ丁寧に説明をするのですが、普段扱ったことのない事務を理解していただくのは大変でした。
中には3回〜5回程度かよってやっと登記ができそうだという方も、いらっしゃいました。
現役の方ではとても時間が取れないのではないかと感じました。
又、大変恐ろしいのは書面の記載方法しかアドバイスしていませんので、実体法上その内容で合意がなされているかどうかチェックする方法がないということです。
登記官も形式的チェックしかしません。
私たち司法書士が、登記申請する場合関係当事者に内容の確認を行いますが
それがなされない申請が増えることは、登記制度の信頼に影響するのではないかと考えさせられました。

過払い金返還の期日について
2009.06.22
先日貸金業者のE社と、債務整理の一環として過払い金の返還交渉を行いました。担当者の説明では、今月和解しても過払い金の返還は、来年の7月になるということでした。大量の返還請求に対応するためとの説明ですが、驚きのあまり二の句が継げませんでした。過払い金については当該業者が過去に不当に利益を得たものであり、できる限り早急に返還すべきものと考えるのは私だけでしょうか?もっとも提訴し判決を得て強制執行するとなれば、ある程度の日数も必要となります。お客様にしてみれば、早く結論を得たい思いが強いでしょうから、悩ましい問題です。


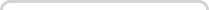

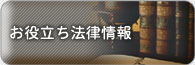
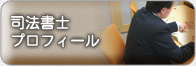



 明日は仙台五大イベントである「仙台青葉まつり」が開催されます。
明日は仙台五大イベントである「仙台青葉まつり」が開催されます。 今、当事務所のホームページ制作が急ピッチで進んでおります。
今、当事務所のホームページ制作が急ピッチで進んでおります。